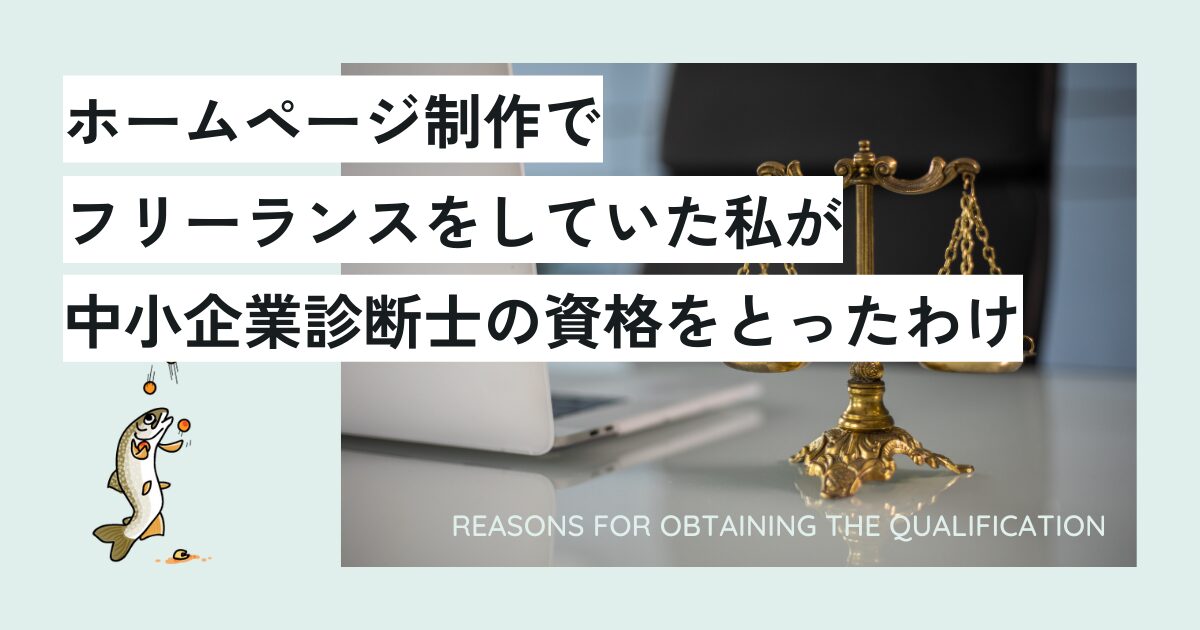旭川でホームページ制作やWebマーケティング、イラスト制作、中小企業診断士業務をしている岩間創作室です。
ホームページ制作をしていると、「集客したい」「採用につなげたい」といった要望をよくいただきます。ですが、その依頼の方向性そのものがずれていると、どんなに見栄えのいいサイトを作っても成果が出ないことがあります。
私は広告代理店のWeb制作部門での勤務を経てフリーランスとなり、2025年に中小企業診断士の資格を取得しました。本記事では、なぜWeb制作者の私が診断士資格を目指したのか、そしてホームページ制作と診断士の知識がどのように結びつくのかをお伝えします。
- 広告代理店のWeb制作部門で約3年半勤務。
- 2020年からフリーランスに転向。
- フィジー留学やカナダでのワーホリ中はWeb制作を兼業する形で行う。
- 本格的にフリーランス活動を始めたのは2022年5月から。
- 2023年末〜2024年初めにかけて診断士の学習を開始。2025年に合格・登録。
中小企業診断士という資格との出会い
きっかけは、とあるブランディング案件でした。
当時依頼されていたホームページで、クライアントから「ブランディングをしたい」という要望がありました。その中で「ブランディングとは何か?」やその手法を調べていたところ、たまたま診断士関連のWebサイトに行き着きました。
正直なところ、それまで診断士という資格を知りませんでした。しかし内容を調べてみると「経営全般を横断的に学べる国家資格」であり、自分の仕事と非常に親和性があると感じました。
資格取得を決意した理由
(1) Web制作と経営課題のつながり
ホームページ制作のゴールは「作ること」ではなく「経営課題の解決」です。
売上を上げたい、採用につなげたい、認知を広げたい……
依頼の方向性そのものが間違っていると、成果は出ません。
依頼側がホームページによって解決したい事項を見誤っていたり、過剰な期待を抱いていることは、正直なところ時々あるように思います。特に、決済者と企業側の広報担当者/Web担当者が異なる場合、担当者は「このパーツを赤くしたい」といった枝葉を気にする傾向があり、根本的な課題解決に向かわないことがしばしばです。
診断士の知識を持つことで、Web制作のさらに上流に踏み込み、経営視点から適切な提案ができるようになると考えました。
(2) 自分自身フリーランスとしての経営改善
フリーランスは「一人企業」としての側面があります。
当時の私は仕事が忙しいときと空いているときの差が大きい状況でした。診断士資格を見つけた際は、ちょうど空き気味で「自分の経営に改善点があるのでは」と感じていました。資格勉強を通じて、自分の事業運営そのものを見直したいという気持ちもありました。
(3) タイミングとチャレンジ
仕事に少し余裕があったタイミングだったため、「暇なら勉強してみよう」という軽い気持ちで始めたのも大きな理由です。勉強自体は好きで得意だったため、比較的短期で合格できるのではという推測もありました。
後述しますが、特にフリーランスにとって標準1,000時間もの時間がとられる資格をとろうとすることはリスクにもなりかねません。そのため、短期でどれるのではという推測は意外と重要です。また、ひとまず勉強は進めても、独占業務がないため実際に受験するかどうかは4月の受験申込期間ぎりぎりまで迷いました。
フリーランスWeb制作者として診断士資格を持つ意義
診断士資格を取ることで、私は単なる「ホームページ制作者」ではなく「経営課題解決に寄り添えるパートナー」として提案できるようになったと考えています。
私がWeb制作者としての初期もそうだったのですが、Webデザイナーやエンジニアの多くが経営はもちろんマーケティングの視点がない人がほとんどだと思います。よくクライアントから「前のホームページ制作会社は提案してくれなかった」という声が聞かれるのも、制作会社またはその担当者にそういった視点がないからではないでしょうか。
診断士資格を取得して、
- 経営戦略やマーケティングを理解した上でサイトを設計
- クライアントの言葉を翻訳し、施策に落とし込む
- 制作だけでなく、事業全体の方向性を踏まえたアドバイス
といったことが可能となったため、「この人に頼めば安心」と思っていただける制作者に近づけたのではと思っています。
中小企業診断士の資格を取ろうと思っているフリーランスの方へ
診断士を目指す方に伝えたいことがあります。
独立診断士はハードルが高い
フリーランスや士業と兼業するケースもありますが、多くは試行錯誤を重ねているようです。資格を取ったからといってすぐに独立し十分に稼げると言う人は少数派と思われます。これには個々のスキルだけでなく、地理的に競合が多いかどうかも影響します。同期診断士の話を聞く限り、東京大阪は案件に対し診断士が多く競争が苛烈な印象、地方は診断士が少ない傾向がありそうです。診断士の数自体も増加しています。
なお、実は診断士の多くは企業に勤めながら資格を活かす「企業内診断士」です。独立して診断士業務を専業にする人やフリーランスと兼業する人は少数派です。
Web制作者やフリーランスには相性が良い
Webやマーケティングに携わっている人にとっては「経営全体の知識」が大きな強みになります。私自身、診断士の学びを通じて提案の説得力が増したと思います。
フリーランスには「ひとり経営者」の側面があるので、自身の事業の改善にもつながるでしょう。
SEOや集客との親和性が高い
「中小企業診断士 × フリーランスの業種」という掛け算は、独自のポジションを築きやすい分野です。資格を取る動機としても十分にありだと思います。
「学習に業務時間が奪われるのに不合格」の可能性も忘れずに
中小企業診断士の資格取得には、標準1,000時間が必要といわれます。まる1年をかけたとして、1ヶ月あたり約83時間、1日あたりでは約2.8時間にもなります。
それだけの時間があれば、かなり稼げるのではないでしょうか? あるいは診断士ではなく、いまのフリーランスの業務知識を深め、単価を上げることに使えるかもしれません。
忘れてはいけないのは、資格試験である以上、合格・不合格があることです。業務時間を削って、収入を削って学んでも不合格、それも複数年にわたることもしばしばです。そのようなリスクも考慮した上で、中小企業診断士の資格勉強と向き合うか考えた方がよいでしょう。
実際に私は1字試験・2次試験の直前1ヶ月は意図的に業務量を落としています。1年で受かったから良いようなもので、これが複数年続いていたらと思うと恐ろしい話です。会社員の受験生から「予備校に20万円使った」という話を聞いたことがありますが、我々フリーランスは独学でも”業務をしない損失”としてそれ以上を失う可能性があります。
岩間創作室の今後の展望
岩間創作室は今後、旭川や地方企業を対象に「ホームページ制作 × 経営支援」という二刀流で支援していきたいと考えています。二刀流と書きましたが、イラスト制作もMEO対策などマーケティングも行なっているのでもはや何刀流なのか何足の草鞋なのかよくわかりませんね。併せて公的機関の業務も行います。
地方ではWebやマーケティングに注力している企業が少なく、競合も弱いため、大きな成果を出せる可能性があります。診断士としての知識を活かしつつ、Web制作を「ただ作るもの」ではなく「経営の成果につながるもの」として提供していきたいと考えています。