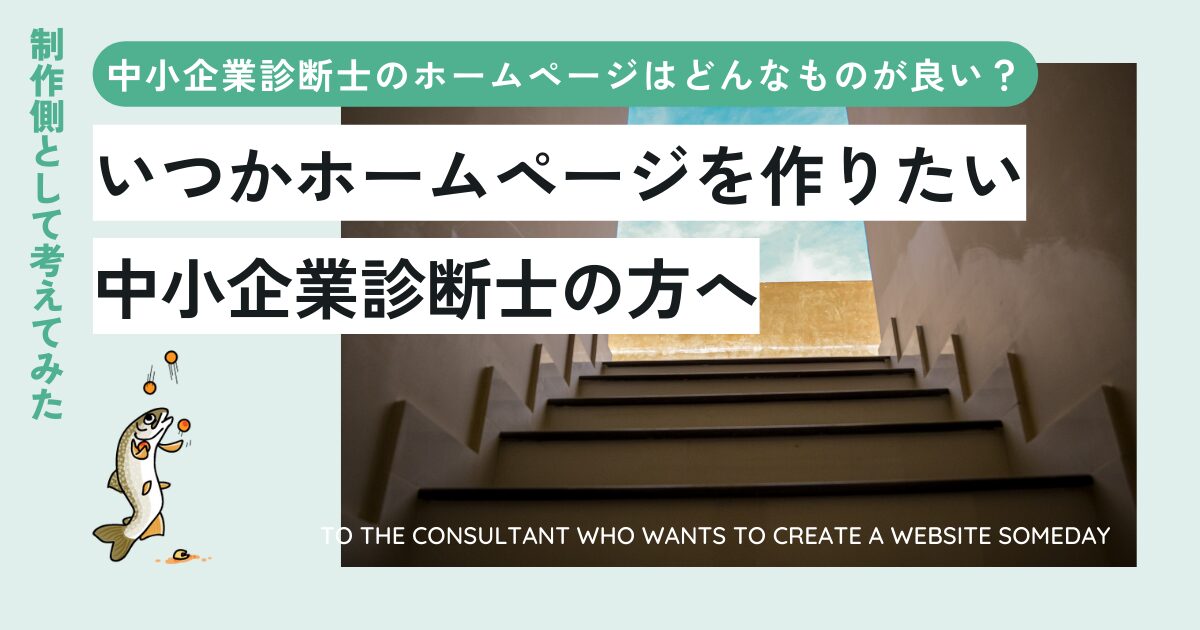こんにちは、北海道旭川でWeb制作・Webマーケティングによる集客採用支援を行なっている岩間創作室です。もともとフリーランスとしてWeb業務を行っており、2025年5月に中小企業診断士となったことで、診断士業務も併せて行っています。
今回は、私自身が診断士でありWeb制作にも携わっていることから、診断士にとってどのようなホームページが適しているのかを考えてみます。
中小企業診断士のホームページに求められる役割
中小企業診断士は税理士や社労士などの他の士業と比べて、業務範囲や提供できる内容が診断士ごとに大きく異なるという特徴があります。経営戦略の立案に強い人もいれば、補助金申請や事業計画書作成を専門とする人もいます。
そのため、ホームページでは以下を丁寧に説明することが欠かせません。
- 自分が提供できる具体的なサービス内容
- 得意とする分野(例:補助金、マーケティング、人材育成など)
- 実績や事例
- 中小企業診断士という資格そのものについて
中小企業診断士という資格の知名度がまだ高くないという現状もあります。知名度が低いからこそ、ホームページで「自分が何をできるのか」を明確にすることが信頼獲得につながります。
ターゲットに応じた記載内容を工夫する
ホームページに掲載する情報は、誰に向けて発信するかによって変える必要があります。
中小企業経営者がターゲットの場合
経営者は「中小企業診断士」というキーワードで検索することは少なく、むしろ「補助金 申請サポート 旭川」「経営改善 コンサル 北海道」「離職防止 札幌」といった具体的な課題ベースで検索することが多いです。そのため、専門用語は控えめにし、分かりやすく解説することが大切です。
公的機関の担当者がターゲットの場合
この場合は「中小企業診断士 旭川」といった、地名と併せたキーワードで検索される可能性があります。公的機関の制度を理解していることや、専門用語の理解度を前提にした情報を掲載すると効果的です。
ターゲットを意識したコンテンツ設計を行うことで、検索エンジンからの流入も増え、見込み客に届きやすいホームページになります。
SEOを意識したホームページ運用
「中小企業診断士 ホームページ制作」で検索上位を狙うためには、以下のようなSEO対策も有効です。
- ブログ記事で「補助金」「経営改善」「マーケティング」などの具体的テーマを発信
- 地域名(例:旭川、中小企業診断士 北海道)を組み合わせたページを作成
- 診断士としての専門分野や強みをキーワードに盛り込む
単にホームページを作るだけでなく、ブログや実績紹介を通して検索されやすい状態を作ることが成果につながります。
特に地方の中小企業診断士では、エリア名を入れることでSEO上のライバルが大幅に減るため非常に有効です。また、リモートで業務が可能な内容についても、経営者のニーズとして「直接会える人」「顔が見える」という条件が重要になる場合もあるので、以外にも地元からの引き合いが強い可能性があります。
事務所がある場合はMEO対策を
オフィスを構えている場合にぜひ取り組んでほしいのが、MEO対策(Googleマップ対策) です。
MEO対策とは、Googleマップ上で自分の事務所を検索結果に表示させ、見込み客に見つけてもらいやすくするための施策です。特に「地域名 × サービス名」で検索されるケースでは、ホームページよりも先にマップ情報が表示されることが少なくありません。
なぜMEOが有効なのか?
- 地域の検索に強い
近くで相談できる専門家を探すとき、多くの人はGoogleマップを使います。 - ホームページよりも目に留まりやすい場合がある
検索画面の上位に地図とともに表示されるため、クリック率が高くなります。マップ順位とSEO順位は連動するとも言われ、SEOにも貢献します。 - 信頼性の向上
実在する事業者であることを簡単に示すことができます。加えて口コミや写真を掲載することで、安心感を与えられます。
実際にやるべきこと
- オーナー確認
Googleビジネスプロフィールに事務所を登録し、正確なビジネス名・住所・電話番号・営業時間を入力。 - 内容を充実させる
事業内容を概要欄に記載し、提供サービスを商品として登録します。写真(外観・内観・スタッフ)も掲載して親近感を高め、問い合わせへの心理的抵抗を少なくします。 - 投稿
ブログとSNSの中間のような機能があります。定期的に投稿機能を使って情報を更新します。 - 口コミ
口コミを集め、返信対応で信頼性を高めます。
MEOはSEOに比べて競合が少なく、数ヶ月で成果が見えやすい施策です。事務所を構えている診断士や士業であれば、ホームページと併用することで集客効果を大きく高めることができます。
Googleマイビジネスの登録・キーワード調査・競合調査・最適化や、投稿・口コミ返信まで、MEO対策を代行しております。旭川だけでなく、オンラインで札幌・帯広・釧路など全道、さらに全国の対応が可能です。
中小企業診断士は差別化の必要性が高まっている
近年、中小企業診断士の登録者数は増加傾向にあります。独立して活動する診断士は少数派ですが、競合は確実に増えています。
だからこそ、ホームページでは以下のような差別化が重要になります。
- 自分の専門分野を明確に打ち出す
- 他の士業や専門家と連携できる体制を示す
- 実際に成果を出した事例を掲載する
「この人なら安心して依頼できる」と思ってもらえるホームページが、中小企業診断士としての信頼と仕事の獲得につながります。
“診断士としての実績がまだない”という声もよく聞かれますが、診断士資格を取るような人の多くが会社員等でかなり経歴を積んでいるケースが見られます。どのような業種で働いてきたか、どのような職種でどんな技能を持っているかといった診断士を取る前からの技能も、顧客からは評価の対象となります。
会社員としての実績もまだ少ない20代でも、大学での専門が生きる場合もありますし、リタイヤを考えている診断士が後継者を探していたり、過去の自分のような存在を助けたいと考えている場合もあります。若くして難関資格を取ったこと自体も評価対象となるので、さまざまな内容が発信対象となるでしょう。
ホームページ制作者からの視点:読みやすさへの配慮
ここからは、特にホームページ制作をしている側が気をつけているテクニカル面の注意事項を書いていきます。
ホームページは「誰に見てもらうか」によって、文章の構成やデザインを調整しています。特に中小企業診断士のように、顧客が多様な層にまたがる場合は、読み慣れている層とそうでない層の違いを意識することが大切です。
文章を読み慣れている層への対応
公的機関の担当者のような、普段からレポートや資料に触れている層であれば、長文をそのまま掲載しても問題ありません。むしろ、具体的な事例や論理的な説明がしっかり記載されていることで信頼を得やすくなります。
読み慣れていない層への対応
一方で、中小企業経営者の中には「長文は読むのが苦手」「ネットではサッと情報を得たい」という方も少なくありません。こうした層に向けては、以下のような工夫が効果的です。
- 段落の間に写真や図解を挟んで視線をリフレッシュさせる
- 箇条書きや見出しを活用し、要点を一目で理解できるようにする
- スマホで見やすいレイアウトにする
こうした配慮をすることで、文章を読み慣れていない層でも最後まで読んでもらえる可能性が高まります。
50代以上をターゲットにする場合の注意点
さらに、ターゲットが50代以上の場合には視認性に関する配慮が不可欠です。加齢に伴う老眼や視力低下を考慮すると、次の点に注意すると良いでしょう。
- 文字サイズは16px以上を基準にし、大きめで読みやすくする
- 背景と文字のコントラストを強めに設定(黒文字+白背景など)
- リンクやボタンは小さすぎず、クリック/タップしやすい大きさにする
- クリックできるボタンは「>」をつけたり立体感で押せることを示す
- 行間を広めにとり、詰め込みすぎないレイアウトにする
読みやすいかどうかの簡単な判断基準は、目を細めたときに少しぼんやり見える状態でも読めるかどうかです。試してみると、似たような色のコントラストが低い文字や、小さい明朝体の文字は読みにくいのではないでしょうか。
見やすさに配慮した設計は、読み手のストレスを減らし、結果的に滞在時間の増加や問い合わせにつながる効果も期待できます。
まとめ:中小企業診断士はホームページで差別化を!
中小企業診断士にとって、ホームページは単なる名刺代わりではなく、専門性を伝え、信頼を得るための大切なツールです。
- 診断士ごとの業務の違いを分かりやすく説明する
- ターゲットに応じた言葉づかいや内容を工夫する
- SEOを意識して検索されやすい状態を作る
- 強みや実績を明確に打ち出す
これらを意識したホームページ制作を行うことで、診断士としての存在感を高め、顧客や公的機関からの依頼につなげることができます。