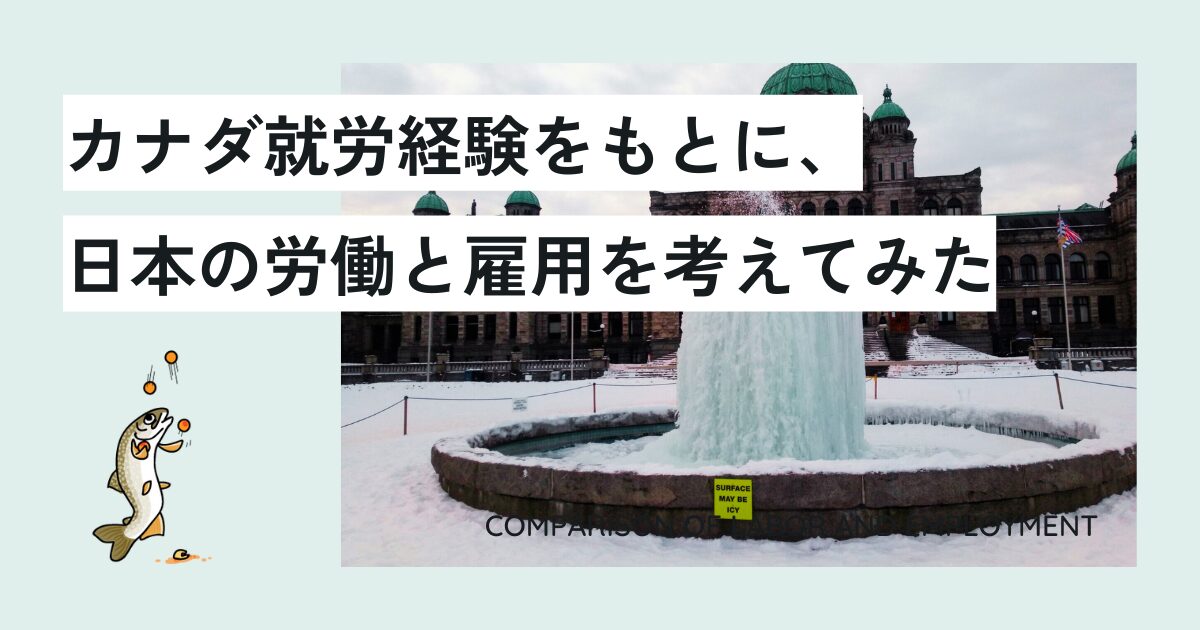こんにちは、旭川でWebマーケティングなどを行なっている中小企業診断士、岩間創作室です。
2021年2月〜2022年5月までワーホリでカナダに滞在していました。期間中の大部分は就労しており、数箇所経験しています。
本記事では、その経験をもとに日本の就労条件や雇用を考えてみたいと思います。
※情報は2025年8月時点のものです。カナダはBC州を比較対象としています。
カナダと日本の法律を比較しながら考察
主観だけでは参考にならないと思うので、まずは法律を参照しながら見ていきたいと思います。
賃金の比較
| 日本(東京都) | 日本(北海道) | カナダ(BC州) | |
|---|---|---|---|
| 最低賃金 | 1,163円 | 1,010円 | 17.85ドル(≒ 1,921円) |
| 割増賃金 | 日本 | カナダ(BC州) |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 1.25倍 | 1.5倍(最初の4時間) |
| 時間外+深夜労働 | 1.5倍 | 2倍(1日12時間超のとき) |
| 休日労働 (カナダは法定休日) | 1.35倍 | 1.5倍 |
| 休日労働+深夜労働 (カナダは法定休日) | 1.6倍 | 2倍(1日12時間超のとき) |
※上記はあくまで概要版です。詳細な就業に関する法規は公式情報を参照してください。
気になる賃金から。
インフレ率の違いに加えて為替の影響もあり、大きく差をつけられています。
私が滞在していた2021年のBC州の最低賃金は15.20ドル、1カナダドル≒100円だったのでやく1,520円。4年前と比べても、かなり上がっています。業種によってはこの金額にチップが乗ります。
ワーホリを出稼ぎ手段にしているというような話題も耳にします。私が滞在していたときも、アルバイトで日本の正社員よりも稼げるような状況がしばしばでした。住居環境と医療の問題(後述)さえクリアできれば快適な生活が送れるのでは。
また、残業時間に対する割増率が異なります。残業時間は、「仕事か家族か」といった価値観の違いだけでなく、割増率も影響すると考えられます。雇用主からすると、カナダの方が「残業をさせたくない」と思うのではないでしょうか。
雇用に関するその他の情報
| 割増賃金 | 日本 | カナダ(BC州) |
|---|---|---|
| 雇用契約の終了(解雇) | 「解雇自由」はなく、合理的・客観的根拠が必要。解雇の場合は30日前の予告、または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)が必要。 | 雇用主は一定の通知期間や手当を支払うことで雇用契約の終了が可能。ただし人権法違反(性別・年齢等の差別)やハラスメントが理由の解雇は禁止。 |
| ハラスメント・差別禁止 | 人権法で雇用差別・ハラスメント等を禁止。男女同一労働同一賃金義務。 | 一労働同一賃金義務。性別・国籍・社会的地位等の差別禁止+ハラスメント防止義務強化。 |
| 履歴書 | 「顔写真・生年月日・性別・本籍」など個人情報の記載が慣習的に求められる。フォーマットがある程度決まっている。 | 「写真・年齢・性別・国籍」の記載を義務付け/要求禁止。選考基準はスキル・経験・業績。フォーマット自由。 |
| 給与支払い頻度 | 契約時に明記。法律で統一支払頻度はなし。 | 月2回以上、詳細な給与明細必須。小切手のことも。 |
解雇規定は日本に比べかなり緩いです。
履歴書の「写真・年齢・性別・国籍」要求禁止は日本との大きな違いでした。また、求人票も業務内容が詳細に記載されていたり、「皿洗い」の募集なら実務も「皿洗い」のみが普通のよう。実際の業務でそれ以外の内容が発生したときは給与を上げてもらえるか交渉の材料となります。
意外な違いとしては、給与が月2回振り込まれるというものもありました。特に低所得者にはありがたい仕組みなのでは。
カナダでの就労と生活

カナダと日本の就労
カナダでの就労形態は非常に多様でした。
週に1日・2時間だけのアルバイトから、鉱山などの僻地で1ヶ月働き1ヶ月休むという特殊な働き方まで耳にしました。日本の一般的な労働スタイルとは大きく異なり、柔軟に働くことができる環境ではないでしょうか。
給与の支払い方法も日本とは違い、小切手で支払われることが一般的です。受け取った小切手は銀行で換金します。最初はびっくりしました。
一方で、カナダは雇用契約の終了に関する法規制が日本に比べて緩やかで、解雇の自由度が高いという特徴があります。事業者としては、時給を高めに設定してもリスクが低くなり、労働者も高い賃金を得られます。働く側は自身に合わない業務に長期間とどまる必要がなく、自分に適した職種や職場を見つけやすい環境になっているとも言えます。ただし、どの職場や職種でもうまく適応できない場合は生活が非常に苦しくなるリスクもあると感じました。
ちなみに実際に働いてみて、労働の質はやはり日本の方が求められ、カナダの方がてきとうです笑。それでいて賃金は日本の方が安いので……
日本の職場で不満が出やすい原因
カナダで仕事の愚痴を聞くことが少なかったのは、単に私の英語力の問題だけでなく、こういった背景もあるように感じます。日本では、苦手な業務ばかりの職場や何らかの不満がある職場にしがみついてしまっている人が多いのかもしれません。
両方の環境で働いた経験から、日本での労働で不満が出るであろう項目も感じました。日本では募集要項では労働内容があまり詳しく記載されておらず、同じ枠に複数人が応募し採用されたにも関わらず違う業務を割り振られることがあります。業務負荷が異なり同じ賃金であれば、不満が出るのも当然ではないでしょうか。
実際に突撃比較してみた
帰国後にアルバイト労働の比較をしようと思い、1日だけホテルのハウスキーピング系の仕事をしたことがあります。ホテルのハウスキーピングはカナダでも経験した内容であり、同じ業種であれば詳しい比較ができると考えてのことです。
まず応募段階で、「女性活躍」などの単語が並び、少々不穏な空気を感じます。カナダではジェンダーギャップ指数が高く(2025年はカナダ32位、日本118位)、日本の状況が違和感として映りました。さらに、履歴書提出時には「顔写真・年齢・性別」を求められました。カナダで1年働いていた自分にとっては、これは明確に「差別します」と言われているようで、不快な印象を受けました。
実際に現場に行ってみると、何の前触れもなく男女で業務を分けられました。おなじ募集で集められた人に対してです。募集でそのようなことは何も記載されていなかったにも関わらず(本当にもうドン引きでした、しかし日本はこれが普通)。これでは不満が出て当然ですし、カナダで同じことをすれば、労働環境において性別による不公平な扱いや役割分担、つまり「差別」として扱われます。
カナダの求人には重量物の運搬に関する具体的な情報が明示されています。例えば「何キログラムの物をどのくらいの頻度で運ぶか」が明記され、それを満たせない場合は解雇の理由にもなります。逆に、労働者にその能力があっても好まない労働内容であれば、労働者は自己判断で避けることが可能です。
日本の求人や業務の割り振りは、まるで男性は男性で・女性は女性で皆均一な能力を持つかのような扱いでした。確かに単一民族の割合が極端に高いので、多様な人種を抱える国に比べればその傾向はあるのかもしれませんが、このような扱いが不満やミスマッチ、離職率の増加の要因になっているように思えてなりません。
カナダでの労働者としての生活

カナダは賃金が高く、税金負担が比較的少ないため、生活は楽に感じられました。
しかし、住居費と医療費についてはかなり高額です。日本のように一人暮らし用の狭い住居はほとんど存在せず、特にワーホリとなると基本的にはシェアハウス生活が一般的です。広い一軒家やファミリー向けのマンションのような場所の1部屋を借り、キッチンやバスルームを共有する形態です。それでも家賃は600ドル前後が標準的な相場です(2021~22年当時のビクトリアやイエローナイフ。バンクーバー等はさらに高額ではと思います)。
医療費は特に高く、歯科治療のためにメキシコまで行く人がいたほどです。そのため、予防医療への意識が高いようで、サプリメントショップが多く存在します。ビクトリアの街ではコンビニよりもサプリメントショップの方が多いほどでした。スーパーにもサプリメントやプロテインのコーナーがまるまる1〜2列設けられています。
日本では数千円で病院にかかれてしまうためでしょう、ドラッグストアでさえもサプリコーナーはわずかです。帰国してから国産をうたうサプリメントを目にしますが、カナダと比べてしまうと日本はサプリ後進国のような状況です。また、サプリメントの売り方も日本では情緒的、カナダは成分と含有量を推しており、購買動機やそれに伴うマーケティングの違いも感じました。
カナダ国内の場所によっては水道水にフッ素が添加されています。私自身は虫歯になりやすい体質で、医療費が高いカナダでどうなることかと思っていましたが、滞在中いちども虫歯になりませんでした。
健康であることさえ保てれば、カナダでの生活は充実したものになるのではないでしょうか。これは、日本の医療制度のすごさ・良さを感じた点でもあります。
日本の求人がカナダから学べること
「日本と海外は違う」と言ってしまえばそれまでですが、確かに違いはあれど、海外で前例があるものを、日本がイチから開発する必要はないのではないでしょうか。過去のデータを参考に、日本をよりよくするのが理想です。巨人の肩の上に乗りましょう。
法律を変えずとも、事業者側でお金もかけず変えられる点は実は数多くあるのではないでしょうか。上記のホテルの求人も、たとえ同じ給与でも応募を2種類に分けるだけでも、同じ価値のある2種類の労働があることが示せます。
できるだけ多くの人が、自身の能力を発揮できる職場で、満足のいく条件で働けるようになってほしいものです。企業側も生産性の高い人材が集まり、離職率が低く、業績を伸ばしていける状態を目指したいですね!